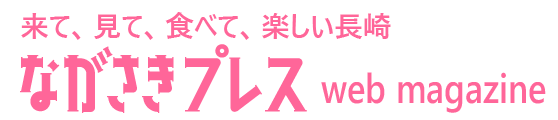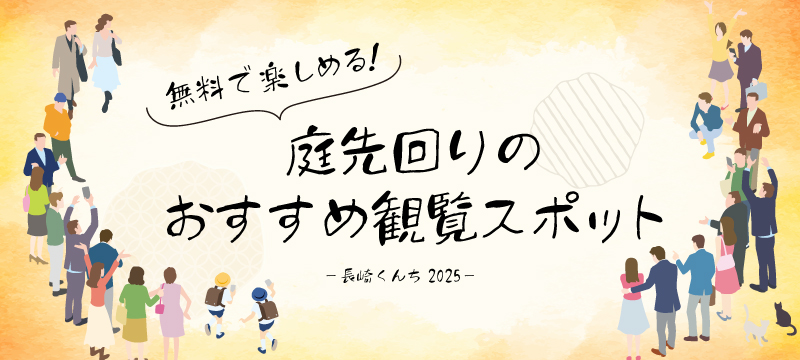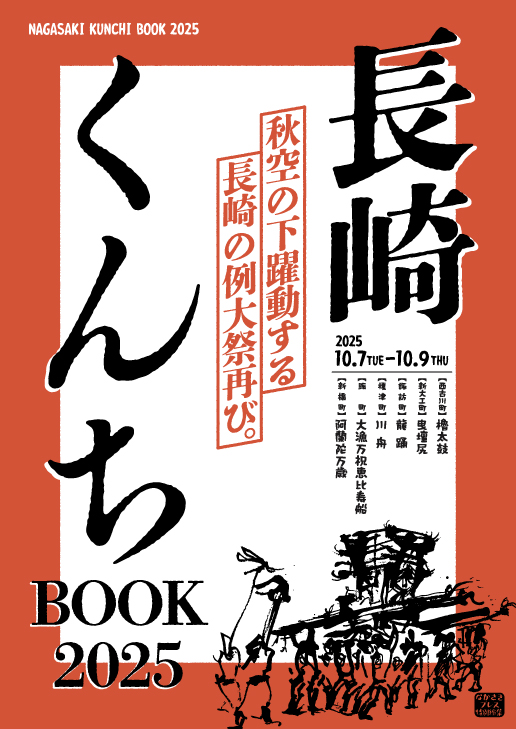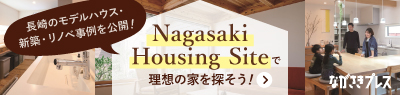長崎くんち - ながさきプレス
Category
踊町:西古川町(櫓太鼓・本踊) 相撲と縁深い踊町が奉納する 力強く心躍る太鼓の音 櫓太鼓とは、相撲場や歌舞伎にて、開場を知らせるために櫓の上で打たれていた太鼓のこと。 長崎は、江戸時代の相撲の興行で、本番所の5場所の中、長崎は九州でただひとつ開催されていたのだとか。 西古川町は享保2年(1717年)より相...
踊町:新大工町(詩舞・曳壇尻) 力強く、スピード感あふれる曳き回しを 艶やかで優美な舞と共に── 諏訪神社のたもとで、今も賑わう商店街を擁する新大工町。 職人町のある中島川沿いのさらに上流に位置していて、その名の通り、たくさんの大工さんが住んでいたという町だ。 大工職人と縁が深いことから、曳壇尻の飾大工の神様が祀られて...
踊町:諏訪町(龍踊) 長崎くんちの代表格・龍踊 天高き秋空に舞う、壮麗な姿に刮目あれ 長崎くんちの奉納踊の中で、最も有名な存在と言っても過言ではない「龍踊」。 五穀豊穣を願う雨乞い神事として中国で踊られていたものが由来している。 かつて諏訪神社が祀られていた場所の門前にあったことが町名の起源である諏訪町では、諏訪神社の...
踊町:榎津町(川船) うねる荒波を越え、突き進む 豪快で華麗な、伝統の船回しは必見! 榎津町は旧町名で、現在の万屋町と鍛冶屋町に編入されたエリア。 かつて筑後の榎津(現在の福岡県大川市)産の家具を取り扱う商人が多かったことから、その名が付けられたのだとか。 川船は、いくつかの町が奉納するが、榎津町のものは...
踊町:賑町(大漁万祝恵美須船) 3隻の船が重厚に、そして華麗に踊る 大漁祈願の豪華な曳き回しは必見! かつて魚市場として栄えていたという賑町。 中島川に架かる賑橋のすぐそばには、漁業・商売繁盛を司る恵美須神社があることから、昭和61年(1986年)より恵美須船を奉納している。 親船である恵美須船は全長5....
踊町:新橋町(本踊・阿蘭陀万歳) 異国と長崎をつなぐ。 そして新しい世代へつなぐ、文化の継承 阿蘭陀万歳は、昭和8年(1933年)に日本舞踊の花柳流研究会で初演されたもの。 それが長崎の検番へ伝わり、評判に。長崎くんちの奉納踊りとして昇華されていたとか。 現在では、この「阿蘭陀万歳」を奉納しているのは、栄町と新橋町のみ...
踊町:玉園町(獅子踊) 諏訪神社のお膝元が披露する 獅子奮迅の勇壮な舞姿 昭和38(1963)年に、旧上筑後町と東上町、そして下筑後町の一部が合併して生まれた玉園町。 「諏訪神社がある、玉園山のふもとの町」から名付けられた。 江戸時代、上・下の筑後町では「筑後獅子」が奉納されていたが、明治に...
踊町:今博多町(本踊) 秋の空を華麗に舞う くんちの起源たる純白の鶴翼 長崎に移り住んできた博多商人たちによって築かれた博多町。 さらに商人が増え、これまでの博多町(現在の興善町付近)が「本博多町」に、そして新しく造られたこの町が「今博多町」となった。 今博多町は、丸山に移る前の花街があった...
踊町:江戸町(オランダ船) 唯一無二の特色を乗せ 日蘭の文化をつなぐ渡り船 長崎奉行所西役所の下に設けられた江戸町は、出島の門前町として江戸から派遣されてきた役人が多く住む町だった。 オランダ船から舶来品などが荷おろしされてきた場でもあったこともあって、江戸町では華やかな西洋文化を表すかのような、カラフル...
踊町:籠町(龍踊) “令和”の新時代、秋空に舞う 伝統と歴史が詰まった新・龍踊 国への貿易用に使う竹籠を作る職人町だったことが、籠町の名の由来。 唐人屋敷に隣接した町として繁栄していたという縁もあり、唐人屋敷から伝わってきた龍踊を奉納している。 数多くの奉納踊の中でも一、二を争う人気を誇り、...