
長い歴史を誇る「ながさきくんち」。その成り立ちや見どころ、公式会場の特徴から、観覧時によく耳にする専門用語までをわかりやすく解説しました。この記事でくんちの魅力をしっかり押さえておきましょう!
もくじ
長崎くんちについて
長崎くんちは、長崎の氏神さま・諏訪神社の祭礼行事(例大祭)。豪華絢爛な奉納踊りで全国的にも有名で、長崎人の心に大きな存在感を放ちつづける、長崎最大の行事のひとつです。毎年10月7日から9日までの3日間に行われており、7日に御神輿がお旅所(大波止)に移られる「お下り」、9日に諏訪神社に戻られる「お上り」などの御神事を中心行事として、神社やお旅所などで奉納踊りが奉納・披露されます。「くんち」の語源は「宮日」「供日」とも言われるが、陰暦9月9日の「重陽の節句」に行われたことから「九日(くにち)」からという説も。
寛永11年(1634年)に、2人の遊女、高尾と音羽が、諏訪神社神前に謡曲「小舞」を奉納したことが、長崎くんちのはじまりだと言わています。
現在、演し物を奉納する踊り町は、全部で58ヵ町が参加している。それが7つの組に区分され、一年ごとに順繰りにめぐっていく。つまり、奉納踊りを出す当番は7年に一度回ってくるのだ。演し物は、龍踊りや鯨の潮吹き、コッコデショなど、町によってさまざま。これらの奉納踊は、国指定重要無形民俗文化財となっている。
今年は西古川町、新大工町、諏訪町、榎津町、賑町、新橋町の6町が出演。コロナ禍などの影響を受けて、当時3年間は延期を余儀なくされたので、7年ごとにめぐる当番町は、実に10年ぶりの出演に。多くのおくんちファンが待ちわびた、最高の3日間が、今年も始まる。
観覧スポット
長崎くんちをガッツリ楽しみたいなら、奉納踊をいい場所で!
基本の観覧場所をしっかり把握しておこう!

諏訪神社
長崎くんちは、この諏訪神社の大祭のこと。諏訪神社での奉納は非常に人気が高く、この踊馬場の席を手に入れるのは一苦労だ。4人掛けの桝席と当日販売の立見席のほか、年によっては桝席の一部がバラ売りで販売されることも。踊場正面の長坂は無料観覧席として開放されている(事前応募~抽選による「長坂整理券」が必要)。
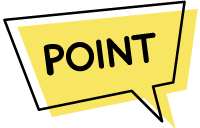
7日と9日の「お下り」「お上り」では、入場料100円で利用できる桟敷席が用意されています!(※席は自由席となっておりますので、予めご了承下さい。)
13時前後のお神輿到着時には、例年長い行列ができるため、観覧希望の方は早めの来場がおすすめです。
長崎市上西山町18-15

お旅所
諏訪神社から三基の御神輿が「お下り」した後、鎮座するための仮宮が設けられる。長崎港に面した平地でバスや電車など交通の便も良好。周辺には多くの露店が並んで、お祭りを堪能しやすい好立地。4人掛けの桝席がある。
長崎市元船町17

中央公園くんち観覧場
中心市街地の近くに位置する中央公園。ベンチシート仕様で、1人単位で観覧券が購入できる。踊場の至近に設置された砂かぶり席は、間近で演し物を観覧可能だ。
長崎市賑町5-100

八坂神社
寺町通りの奥に位置していて、長崎市民から「ぎおんさん」と呼ばれ親しまれている。踊場と観覧席が近く、臨場感満点の演し物を観ることができる。4人掛けの桝席がある。
長崎市鍛冶屋町8-53
長崎くんち 専門用語辞典
庭見世 [にわみせ]
10月3日。夕刻から各踊町の家々では表格子をはずし、床飾り、生け花などをしつらえ、木戸口を開放するなどして、家の中や庭園を道行く人に見せる。表通りに面した家々には傘鉾をはじめ演し物の曳物・衣裳・小道具・楽器などを分散して飾り、出演者に贈られたお祝品を並べ披露する。
傘鉾[かさぼこ]
傘鉾は、踊町の「象徴」であり「町印」。奉納踊りの行列の先頭に立ち、町内の何人たりとも、その前に立つことは許されない神聖なもの。「傘鉾に町の歴史を教えられ」とも言われる傘鉾は、町の象徴であり、神事や町の由来、奉納踊りに因む装飾を「だし」や「たれ」に盛り込み「わが町はこのような歴史があり、このような踊りを奉納いたします」といったことを表現する。
踊町(年番町)[おどりちょう(ねんばんちょう)]
奉納踊りを出す当番の町は7年に1度回ってくる。現在は58町を7つの組に分けている。各踊町は、町の神聖な象徴としての傘鉾と、それぞれに創意工夫を凝らした演し物を神前に奉納する。また、奉納から4年目に年番町を務める。年番町は、氏子として、その年の諏訪神社の神事祭礼へ参列や奉仕(お世話)等を担い、「お下り」「お上り」の行列への参加や御旅所での奉仕、踊町の世話など、重要な役割を果たす。
人数揃い[にいぞろい]
10月4日。「演し物の練習が立派に仕上がったので、くんち当日の本番前にその町内数ヶ所でこれをご披露する」という趣旨のもの。この日はじめて本番と同じ衣裳で、本番通りの奉納踊りを披露する。「庭見せ」が対外的行事なのに対して、人数揃いは町内の人に仕上がりを披露する町内行事。各踊町で、4日の昼すぎから行われる。
お下り・お上り[おくだり・おのぼり]
10月7日13時から、諏訪神社の神様が大波止のお旅所に出かけられることを「お下り」、9日13時から諏訪神社へ神様がお戻りになる事を「お上り」と言う。三体の御神輿とお供の行列。お供には、年番町の子供達が参加する。御神輿を担ぐ(守る→もる)のは旧長崎郷の人たちで、6年に1度当番が回ってくる。お上りでは、諏訪神社下の馬町から神社まで3体の神輿が約200段の石段を一気に駆け上がる「守り込み」が見どころ。
お旅所[おたびしょ]
くんち期間中、3体の御神輿が鎮座する仮宮。元船町の大波止に設けられ人々が参拝に訪れる。










